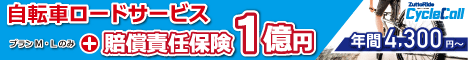- なぜあなたの腕が50kmで限界を迎えるのか、その本当の理由
- プロも実践する、腕の力をゼロにする「体幹主導フォーム」3つの秘訣
- 明日から試せる、正しいフォームを身につけるための具体的な練習法
- 「ポジション沼」を回避し、根本解決に至るまでの最短ロードマップ
- それでも改善しない時に見直すべき「バイク以外の要因」と最終手段

はじめに
「今日も50km過ぎから腕がジンジンする…」
「憧れのしまなみ海道、このままじゃ仲間に迷惑をかけてしまう…」
「初挑戦の緊張感、走りきれるのか不安…」
ロードバイクに乗り始めた誰もが夢見る100kmライド。しかし、その手前で立ちはだかる「50kmの壁」と、じわりと広がる腕の痛み。その悔しさ、痛いほどよくわかります。
ですが、ご安心ください。その腕の疲れは、あなたの筋力不足だけが原因ではありません。実のところ、多くは知らず知らずのうちに身につけてしまった「乗り方のクセ」と「バイク設定のズレ」が引き起こしているのです。
この記事では、ロードバイクで腕が疲れる根本原因を解き明かし、理想のフォームを習得するための完全ガイドをお届けします。
衝撃の事実!あなたの腕が疲れる5つの「勘違い」

あなたの腕が疲れるのは、単に「腕で体重を支えている」からではありません。
その背景には、安全への恐怖心や間違った思い込みなど、多くのライダーが陥りがちな5つの「勘違い」が潜んでいます。腕に体重が乗るのはあくまで結果であり、その根本には見過ごされがちな原因があるのです。
さて、あなたが無意識のうちにやってしまっているかもしれない、5つの「勘違い」を一緒にチェックしてみましょう。
勘違い①:ハンドルは「強く握る」のが安全だ?【恐怖心が生む力み】
ロードバイクに乗り始めたばかりの頃、転倒への恐怖心からハンドルバーをギュッと握りしめていませんでしたか? ふと、これが腕の疲労を引き起こす最大の原因の一つになっているかもしれません。
ハンドルを強く握りしめると、腕の筋肉は常に緊張状態となります。すると、路面から伝わる細かな振動をすべて腕で受け止めてしまうでしょう。
この絶え間ない振動の蓄積が、手のひらの痺れや手首の痛み、そして腕全体の疲労へと直結してしまうのです。
【解決策】
ハンドルは「カゴの中の小鳥を優しく包むように」握るのが正解です。ブラケットには指を軽く引っ掛ける程度で十分。これだけで腕の緊張がフッと抜け、バイクの挙動もより自然に感じられるようになるはずです。
勘違い②:腕は「突っ張り棒」のように伸ばすべき?【衝撃吸収の放棄】
深い前傾姿勢を維持しようと、無意識に腕をピンと伸ばしきってハンドルに体重を預けていませんか。その瞬間、あなたの腕は衝撃を吸収するサスペンションではなく、ただの「突っ張り棒」と化してしまいます。
これでは路面からの衝撃が吸収されず、手首、肘、そして肩や首にまでダイレクトにダメージとして蓄積されていきます。
ライドの後半に決まって肩こりや首の痛みを感じる場合、この「突っ張り腕」が原因である可能性が非常に高いでしょう。
【解決策】
肘は常に「軽く曲げ、ゆとりを持たせる」ことを意識してください。この「ゆとり」こそが、路面からの不快な衝撃を吸収してくれる、高性能な天然のサスペンションの役割を果たすのです。
勘違い③:前傾姿勢とは「背中を丸める」ことだ?【体幹が死ぬ猫背の罠】
「前傾姿勢」と聞くと、つい「猫背」のような姿勢をイメージしてしまいがちです。しかし、これも大きな誤解です。不自然に背中を丸めると、重心が前に偏りすぎてしまい、結果的にハンドルへの体重負荷が増大します。
さらに、胸郭が圧迫されることで呼吸が浅くなり、最も重要な「体幹」の力も使いにくくなるという、まさに負のスパイラルに陥ってしまうのです。
【解決策】
正しい前傾姿勢は「骨盤から」始まります。お辞儀をするように、股関節を支点にして体を前に倒すイメージを持つことが重要です。背中は無理に丸めず、自然で大きなアーチを描くことを意識しましょう。
勘違い④:ペダリングは「踏む」力だけで進む?【上半身と下半身の悪しき連動】
「一生懸命ペダルを踏んでいるのに、なぜか腕が疲れる…」そう感じたことはありませんか。その原因は、ペダリングの方法にあるのかもしれません。
ペダルを真下に強く「踏む」意識が強すぎると、その反作用で体全体が浮き上がろうとします。
すると身体はバランスを取るため、無意識のうちに腕でハンドルを地面の方向へ強く押さえつけてしまうのです。
これこそが、ペダリングと腕の疲れの悪しき連動といえるでしょう。
【解決策】
ペダルは「踏む」のではなく「回す」意識を持ちましょう。踏み込むだけでなく、ペダルが一番下を通過したら「靴の裏についたガムを剥がすように」後ろに引き、そして上に引き上げる意識を持つだけで、上半身の力みが驚くほど抜けていきます。
勘違い⑤:フォームは「一度覚えたら変えない」ものだ?【積極的休養の欠如】
同じ姿勢を長時間続けることが、疲労の最大の原因であることは言うまでもありません。多くのライダーは、一度決めた「理想のフォーム」で走り続けようとしますが、人間は精密な機械ではないのです。
【解決策】
ライド中は、意図的に「フォームを使い分ける」ことを覚えましょう。
- 登り坂やリラックスしたい時: ハンドルの上部(上ハン)を握って上半身を起こす
- 平地の巡航時: 最も基本となるブラケットポジション
- 高速走行や向かい風の時: ハンドルの下部(下ハン)を握って前傾を深める
このように状況に応じて握る位置を変えることで、特定の筋肉に疲労が集中するのを防ぎ、持続的に走り続けることが可能になります。これを「アクティブレスト(積極的休養)」と呼びます。
腕を”空気”にする!「体幹主導フォーム」3つの核心と体重移動のコツ

腕の疲労から解放される鍵は、体の中心「体幹」にあります。
上半身の重さを腕ではなく体幹で支えるための3つの核心「骨盤を立てる」「丹田に重心を置く」「肩甲骨から腕を生やす」をマスターすれば、腕は本来の役割であるバイク操作に専念できるでしょう。
さて、5つの勘違いを理解したところで、いよいよ本題です。腕を「体を支える柱」という重労働から解放し、「バイクを巧みに操るアーム」という本来の役割に戻してあげるための具体的な方法を、3つのステップで解説します。
核心①:「骨盤を立てる」感覚を掴む【全ての土台は坐骨にあり】
全ての土台となるのが「骨盤」です。まずは椅子に座って、その感覚を掴んでみましょう。
- 椅子に深く腰掛け、わざと猫背になってみてください。
- 次にお尻の肉を左右にかき分けるようにして、お尻の下にある尖った2つの骨(坐骨)が座面にしっかりと当たるのを感じます。
- その坐骨の上に、背骨を一本ずつ丁寧に積み上げていくイメージで、スッと背筋を伸ばします。
この「坐骨で座る」感覚こそが、「骨盤を立てる」ということ。ロードバイクのサドルの上でも、この感覚を再現することが、体幹主導フォームへの最初の、そして最も重要なステップになります。
核心②:「おへその下(丹田)」に重心を置く【ハンドル荷重が消える意識】
骨盤を正しく立てることができたら、次はその骨盤の上に上半身の重みをドシっと預ける意識を持ちます。
意識を集中させるのは、おへその指3本分下にある「丹田(たんでん)」と呼ばれる場所です。ここに上半身の重心を置き、全ての重みをサドルとペダルに預けるイメージです。
この意識を持つだけで、今までハンドルにかかっていた体重がスッと抜け、体幹に乗り始めるのを感じられるはずです。
理想的な体重配分は、サドルに約60%、ペダルに約30%、そしてハンドルにはわずか10%と言われています。腕が疲れるという方は、このハンドルへの荷重が20%、30%と異常に高くなっているケースがほとんどなのです。
核心③:肩甲骨から「腕を生やす」【リラックスしたハンドル操作の実現】
体幹で上半身を支えられるようになったら、最後に腕の役割を再定義します。
あなたの腕は、肩から生えているのではありません。
背中にある大きな「肩甲骨」から生えているとイメージしてみてください。ハンドルを操作する時、肩や腕の力ではなく、この肩甲骨から動かす意識を持つことで、肩周りの無駄な力が抜けて、驚くほどリラックスした状態でハンドルを保持できるようになります。
脇は軽く締め、肘は自然に内側を向くのが理想的な状態でしょう。
自宅でできる!壁を使った「体重をかけない」感覚の習得ドリル
いきなり実走で試すのが不安な方のために、自宅で安全にできる簡単なドリルをご紹介します。
- 壁から1メートルほど離れて立ちます。
- 腕立て伏せのような姿勢で、両手を壁につきます。
- この時、腕の力で壁を押すのではなく、お腹にキュッと力を入れて(ドローイン)、体幹の力で体を支えることを意識します。
- 腕の力を抜き、肘を軽く曲げても体が支えられる感覚を掴みます。
このドリルは、ハンドルに体重を預けない「体幹で支える」感覚を安全に養うのに非常に効果的です。
【応用編】ライド中にできる「体重移動」3つのコツで腕の負担を激減させる
体幹で支えるフォームが身についてきたら、さらにライドを楽にするための応用テクニック「体重移動」にも挑戦してみましょう。
- 平地巡航中: 意識的に重心を少し後ろに移動させ、ペダルに体重を乗せる感覚を強めます。
- 緩やかな登り: サドルの少し後ろに座り、骨盤を立てて体幹で上体を引き上げます。
- 少しきつい登り: サドルの前方に座り(前乗り)、ペダルに効率よく体重をかけます。
このように、路面の状況に合わせて積極的に重心を移動させることで、腕への負担をさらに軽減し、より効率的なペダリングが可能になります。
▼体幹トレーニングを自宅で始めるなら▼ おすすめ商品はこちら
フォーム改善でも疲れるなら?お金をかけずに試すポジション調整術

正しいフォームを意識しても腕が疲れる場合、原因はバイクの「ポジション」にあるかもしれません。専門的なフィッティングの前に、まずはお金をかけずに自分でできるサドルとハンドルの基本調整を試しましょう。
これだけで劇的に改善するケースも少なくないのです。
「フォームは意識しているのに、まだ腕が疲れる…」
ご安心ください。それはあなたの努力が足りないわけではありません。どんなに良いフォームを意識しても、そもそもバイクのサイズやセッティングがあなたの身体に合っていなければ、それは絵に描いた餅です。
高価なパーツ交換や専門的なフィッティングに踏み切る前に、まずはお金をかけずに自分で試せるポジション調整術をご紹介します。
まずはココから!サドル高と前後位置が腕の疲れに与える絶大な影響
ロードバイクのポジション調整において、全ての土台となるのが「サドルの位置」。特にサドルの高さと前後位置は、骨盤の角度を決定づけ、上半身のフォーム、ひいては腕への負担に絶大な影響を与えます。
- サドルが高すぎる/低すぎる: 効率的なペダリングができず、余った体重がハンドルにかかってしまいます。
- サドルが前すぎる: 重心が前に寄りすぎ、ハンドルへの荷重が必然的に増大します。
まずはサドルの位置を疑うことが、ポジション調整の第一歩です。
自分でできるサドル高の基本調整:「かかと乗せ法」と「股下×0.885」の計算式
サドル高の調整には、古くから知られる2つの基本的な方法があります。
① かかと乗せ法
- バイクを壁際などに固定し、サドルにまたがります。
- ペダルが一番下(6時の位置)に来るようにクランクを回しましょう。
- かかとをペダルに乗せ、膝がピンと伸びきる高さにサドルを調整します。
これはあくまで簡易的な方法ですが、大まかな高さを知る上では非常に有効です。
② 計算式を用いる方法 より客観的な数値を求めるなら、計算式を使いましょう。
- 取得方法: まず、壁を背にして直立し、股の間に硬めの本などを挟み、地面からその上辺までの長さを測ります。これがあなたの「股下寸法」です。
- 計算式: サドルの高さの目安 = 股下寸法×0.885
- 結果: この「0.885」という係数は、多くのライダーにとって最適なサドル高を導き出すための経験的な数値です。まずはこの数値を基準に調整し、そこから数ミリ単位で乗りやすい高さを探ってみてください。
| 調整方法 | メリット | デメリット |
| かかと乗せ法 | 特別な道具が不要で、誰でも簡単にできる | あくまで目安であり、正確性に欠ける |
| 計算式(股下×0.885) | 客観的な数値を基準にできる | 股下の測定が正確でないと意味がない |
ハンドルの高さと距離、一度に見直すべきポイントとは?
サドルの位置が決まったら、次にハンドルとの位置関係を見直します。腕の疲れに直結するのは、主に「ハンドルの高さ(落差)」と「ハンドルまでの距離(リーチ)」です。
- ハンドルが低すぎる/遠すぎる: 上半身が過度に前傾・伸展することになり、腕で体重を支えざるを得なくなります。
初心者の場合、サドル上面とハンドル上面の高さの差(落差)は5cm以内が推奨されています。
もしメジャーで測ってみて、それ以上にハンドルが低い場合は、スペーサーを入れ替えてハンドルを高くする(またはステムを反転させる)ことで、腕への負担が劇的に軽減されることがあります。
それでも解決しないなら「機材」を疑う【ポジション沼を回避するパーツ選び】
自分でできる調整を試しても改善しない場合、次に考えるべきは機材、つまりパーツの交換です。しかし、これが危険な「ポジション沼」への入り口でもあります。やみくもにパーツを交換する前に、以下の点を考慮しましょう。
- バーテープやグローブ:
最も手軽で費用対効果が高いのが、衝撃吸収性の高いゲル入りバーテープや、パッド付きのグローブへの交換です。これらは路面からの微振動を効果的に吸収し、手の痺れや疲労を和らげます。 - ステム:
ハンドルまでの距離が遠いと感じる場合、現在ついているものより10mm〜20mm短いステムに交換すると、楽なポジションになることがあります。 - ハンドル:
アルミ製のハンドルから振動吸収性に優れたカーボン製のハンドルに交換すると、腕に伝わる微振動が大幅に減少し、ロングライドでの快適性が格段に向上します。
ただし、これらのパーツ交換はあくまで対症療法的な側面もあります。根本的な解決を目指すなら、次のステップを検討する価値があるでしょう。
【最終手段】プロのバイクフィッティングという賢明な自己投資

自己流の調整には限界があります。
専門家によるバイクフィッティングは、あなたの身体をミリ単位で測定・分析し、科学的根拠に基づいて最適なポジションを導き出すサービスです。
無駄なパーツ交換を繰り返す「ポジション沼」を回避し、根本的な解決を目指すための最も確実で賢明な自己投資と言えるでしょう。
ここまで様々な対策を試しても、まだ腕の疲れが解消されない…そんなあなたに残された、最も確実で効果的な解決策が「プロによるバイクフィッティング」なのです。
バイクフィッティングとは?自己流調整との決定的な違い
バイクフィッティングとは、一言で言えば「あなたの身体にバイクを最適化させる」専門的なサービスです。
自己流の調整が、雑誌やネットの情報に基づいた「最大公約数的な正解」を探す作業だとすれば、フィッティングは、専門家があなたの骨格、柔軟性、筋力、さらには過去の怪我の履歴までを考慮し、「あなただけの唯一無二の正解」を導き出す作業と言えます。
専門家は、なぜその角度なのか、なぜそのパーツが必要なのかを、バイオメカニクスの観点から論理的に説明してくれます。もう、感覚だけに頼った当てずっぽうの調整を繰り返す必要はありません。
料金は?時間は?「フィッティングで聞かれること」を全公開
「フィッティングって高そう…」
「何を聞かれるか分からなくて不安…」
そんな疑問や不安を解消するために、一般的なフィッティングの流れと、よく聞かれる質問項目をここで公開します。
【一般的なフィッティングの流れ】
- カウンセリング(30分〜): ライディングスタイル、目標、現在の悩みなどを詳しくヒアリング。
- 身体測定・アセスメント(30分〜): 股下、腕の長さなどの身体測定や、柔軟性のチェック。
- ライディング分析(60分〜): 実際にバイクに乗ってペダリングする様子をカメラなどで撮影し、フォームを分析。
- ポジション調整(60分〜): 分析結果に基づき、サドル、ハンドル、クリートなどをミリ単位で調整。
- 最終確認・アドバイス: 調整後のポジションで再度ライディングし、感覚を確認。今後のアドバイスなど。
料金の目安: 簡易的なもので15,000円程度から、詳細なもので30,000円〜50,000円程度が相場です。
【当日よく聞かれることリスト】
- ロードバイク歴はどのくらいですか?
- 一週間(一ヶ月)にどのくらいの距離を走りますか?
- 主なライドの目的は何ですか?(ロングライド、ヒルクライム、レースなど)
- 現在の具体的な悩みは何ですか?(腕の疲れ、腰痛、膝の痛みなど)
- 過去に大きな怪我や手術をした経験はありますか?
- 今後の目標(例:100km完走、しまなみ海道走破)を教えてください。
事前にこれらの質問への答えを準備しておくと、当日スムーズにフィッティングを進めることができます。
あなたはどっち?静的(スタティック)と動的(ダイナミック)フィッティングの選び方
フィッティングには、大きく分けて2つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選びましょう。
| 比較項目 | スタティックフィッティング(静的) | ダイナミックフィッティング(動的) |
| 内容 | バイクにまたがった静止状態で身体を測定し、理想的な角度を導き出す | 実際にペダリングしている動きを3Dモーションキャプチャなどで分析する |
| メリット | 比較的短時間で、費用が抑えられる | 個々の身体の癖や動きまで考慮した、より精密な調整が可能 |
| デメリット | ペダリング中の動的な動きは考慮されない | 費用が高く、時間がかかる傾向がある |
| おすすめな人 | 初心者の方、まずは基本的なポジションを知りたい方 | より高いパフォーマンスを求める方、痛みが深刻な方 |
なぜフィッティングが「ポジション沼」を回避する最短ルートなのか?
ステムを買い替え、ハンドルを試し、サドルをいくつも渡り歩く…その総額は、あっという間にフィッティング料金を超えてしまいます。
バイクフィッティングは、決して安い投資ではありません。とはいえ、科学的根拠に基づいた最適解を一発で導き出すことで、無駄なパーツ購入の連鎖、いわゆる「ポジション沼」からあなたを救い出してくれます。
それは、あなたのロードバイクライフを一生モノにするための、最も賢明な自己投資と言えるでしょう。
フォームを支える身体作り|ライダー向け体幹トレーニング3選

どんなに完璧なフォームやポジションを手に入れても、それを維持するための身体がなければ意味がありません。
腕の疲労を根本から断ち切るために、ロードバイクの姿勢維持に直結する3つの効果的な体幹トレーニングで、ブレない身体の土台を作り上げましょう。
ここまで、フォームとポジションという、いわば「技術」と「環境」について解説してきました。しかし、これらを最大限に活かすためには、最後のピースである「身体」そのものを鍛えることが不可欠です。
なぜロードバイクに「体幹」が不可欠なのか?その科学的根拠
ロードバイクにおける体幹(コア)は、単に上半身を支えるだけでなく、下半身で生み出したパワーを効率よくペダルに伝えるための「橋渡し」の役割を担っています。
この「橋」がグラグラと不安定では、パワーはロスしてしまい、上半身はバランスを取るために余計な力みを強いられます。その結果として腕に負担が集中するのです。
ブレない体幹を手に入れることこそ、腕の疲労対策として最も効果的な戦略といえるでしょう。
①プランク:姿勢維持の王道トレーニング
数ある体幹トレーニングの中でも、最も基本的で効果的なのがプランクです。
- ターゲット: 体幹筋(腹筋、背筋)
- 方法:
- うつ伏せになり、両肘とつま先を床につきます。
- 頭からかかとまでが一直線になるように意識し、体を持ち上げましょう。
- お尻が上がったり下がったりしないように注意し、その姿勢をキープします。
- 目安: まずは30秒キープから始め、徐々に時間を延ばしていきましょう。
- 効果: この地味なトレーニングが、ライド中の姿勢維持能力を劇的に向上させます。
②クラムシェル:ペダリングを安定させる中臀筋の強化
ペダリング中の骨盤の安定性に大きく関わるのが、お尻の横にある「中臀筋」です。この筋肉を鍛えることで、ペダリング中の左右のブレが減り、上半身が安定します。
- ターゲット: 中臀筋
- 方法:
- 体の左側を下にして横向きに寝て、両膝を軽く曲げます。
- かかとはつけたまま、右膝をゆっくりと上に開いていきましょう。
- 骨盤が後ろに倒れないように注意しながら、お尻の横の筋肉が使われているのを意識してください。
- ゆっくりと膝を閉じ、これを繰り返します。反対側も同様に行います。
- 目安: 左右それぞれ15回×2セットから始めましょう。
- 効果: 臀部の筋肉を強化し、骨盤を安定させ、腕への負担を軽減します。
③キャット&カウ:背骨の柔軟性を高め、リラックス効果を促す
最後に、トレーニングだけでなく、柔軟性を高めるストレッチも取り入れましょう。キャット&カウは、背骨周りの筋肉をほぐし、リラックスさせるのに効果的です。
- ターゲット: 背骨、体幹筋
- 方法:
- 四つん這いになります。
- 息をゆっくり吐きながら、猫のように背中を丸めていきます。おへそを覗き込むように意識します。
- 次に、息を吸いながら、牛のように背中を反らせていきましょう。目線は斜め上に向けます。
- この動きをゆっくりと繰り返してください。
- 目安: 10回程度、呼吸に合わせて行いましょう。ライド前のウォーミングアップや、ライド後のクールダウンにも最適です。
ロードバイクの腕の疲れに関するQ&A

ここでは、多くのライダーから寄せられる、腕の疲れに関するよくある質問にお答えします。
- 衝撃吸収性の高いバーテープやグローブは効果がありますか?
はい、非常に効果的です。特にゲル入りの厚手のバーテープやパッド付きのグローブは、路面からの微振動を大幅に軽減し、手の痺れや腕の疲労を和らげます。
フォームやポジションの見直しと並行して行うと、さらに快適性が向上するでしょう。
- ライド中にできる簡単なストレッチはありますか?
はい、あります。安全な場所に停車し、腕を胸の前で交差させて肩甲骨を伸ばしたり、手首をゆっくり回したりするストレッチが有効です。
また、ライド中にこまめにハンドルの握る位置(上ハン、ブラケット、下ハン)を変えること自体が、特定の筋肉への負荷を分散させる効果的な方法です。
- アルミハンドルとカーボンハンドルでは、疲れ方は違いますか?
はい、異なります。カーボンは素材の特性上、振動吸収性が非常に高いため、同じ距離を走ってもアルミハンドルに比べて腕に伝わる微振動が少なく、疲労が蓄積しにくい傾向があります。
高価ではありますが、ロングライドでの快適性を追求する上では有効な投資です。
まとめ:腕の痛みからの卒業。本当の楽しさが、しまなみ海道であなたを待っている

ロードバイクにおける腕の疲れは、単なる筋力不足ではありません。「フォーム」「ポジション」「身体」という3つの要素が複雑に絡み合った結果なのです。
この記事で解説した内容を、もう一度おさらいしましょう。
- 原因を正しく知る: まずはハンドルを強く握りすぎる、腕を突っ張るなどの「5つの勘違い」に気づくこと。
- 体幹で乗る: 腕の力を抜き、「骨盤を立てる」ことを土台とした体幹主導フォームを習得すること。
- ポジションを最適化する: 自分の身体に合ったサドル位置やハンドル位置を見つけること。
- 身体を作る: フォームを維持するための体幹トレーニングを継続すること。
腕の痛みから解放された時、あなたは本当の意味で風と一体になり、ペダルを漕ぐ純粋な楽しさを再発見できるはずです。痛みではなく、目の前に広がる景色や、仲間との会話に集中できるライドは、これまでの何倍も充実したものになるでしょう。
まずは明日、いや、今日の夜にでも、椅子に座って「骨盤を立てる」練習から始めてみませんか? そして次のライドでは、「ハンドルを優しく握る」ことだけを意識してみてください。
その小さな一歩が、あなたを50kmの壁の向こう側へ、そして憧れのしまなみ海道へと連れて行ってくれるはずです。もし一人で解決するのが難しいと感じたら、いつでも私たちのようなプロを頼ってください。あなたの挑戦を、心から応援しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献・引用元リスト
- ACTIVIKE. (2025, January 8). エアロポジションをキープするために必要な筋肉と鍛え方. Retrieved September 17, 2025, from https://activike.com/2025/01/08/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E7%AD%8B%E8%82%89/
- ACTIVIKE. (2025, January 22). 【サイクリスト必見!強度が高いと腰が痛くなる時の原因と対策】. Retrieved September 16, 2025, from https://activike.com/2025/01/22/%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E5%BF%85%E8%A6%8B%EF%BC%81%E5%BC%B7%E5%BA%A6%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%84%E3%81%A8%E8%85%B0%E3%81%8C%E7%97%9B%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B/
- Bicycle Club – FUNQ. (n.d.). 肩甲骨を意識したフォームを習得! 呼吸がラクになる上半身の使い方|ヒルクライムは筋肉で攻略. Retrieved September 16, 2025, from
https://www.funq.jp/bicycle-club/article/798698/ - チャリストック. (n.d.). まずはフィッティング!ロードバイクの最適ポジション. Retrieved September 16, 2025, from
https://charistock.jp/roadbike/fitting/ - サイクルガジェット. (n.d.). ロードバイクを運転しているときの、手のひらのしびれ&痛みを解消する方法. Retrieved September 16, 2025, from
https://www.cycle-gadget.com/HowToPreventNumbnessOrPain.html - シクロワイアード. (n.d.). より速く快適に ライダーを最適ポジションへ導くバイクフィッティング. Retrieved September 16, 2025, from
https://www.cyclowired.jp/microsite/node/275233 - えふえふぶろぐ. (n.d.). 初心者だけではない!? ロードバイクの乗り方に迷ったらまずはコレ!というお話. Retrieved September 16, 2025, from
https://ff-cycle.blog.jp/archives/1078608174.html - ENJOY SPORTS BICYCLE. (n.d.). スポーツ用自転車で生じる痛み 部位別の原因と対策まとめ. Retrieved September 16, 2025, from
https://www.sbaa-bicycle.com/article/2429 - ENJOY SPORTS BICYCLE. (n.d.). ロードバイクビギナーが覚えておきたい体の痛み対策のまとめ. Retrieved September 16, 2025, from
https://www.sbaa-bicycle.com/article/3616 - 飯田橋カイロプラクティック・整体院 12twelve. (n.d.). 自転車のスポーツ障害. Retrieved September 16, 2025, from
https://iidabashi-chiropractic.com/report/category/sports-injury/%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%A6/ - 膝が痛くなったり腕が疲れたりするのはなぜ? 体の専門家に聞く、ロードバイクのお悩み解決講座. (n.d.). Retrieved September 16, 2025, from
https://d32v8g8s7t6j6r.cloudfront.net/mg/2020/02/causes-of-pain-and-remedies/ - Liv Cycling. (2021). キレイなフォームのポイント|ライディングガイド. Retrieved September 16, 2025, from https://www.liv-cycling.jp/liv21/guides/riding-guide/riding-guide-2.php
- R×L. (n.d.). 自転車(サイクリング)で鍛えられる筋肉ってどこ? 6ヶ所の部位をご紹介!. Retrieved September 16, 2025, from
https://shop.rxl.jp/blogs/column/roadbike-muscle-bike - SAIPROX. (n.d.). ロングライドを疲れず快適に走る秘訣. Retrieved September 16, 2025, from https://saiprox.com/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%92%E7%96%B2%E3%82%8C%E3%81%9A%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%81%AB%E8%B5%B0%E3%82%8B%E7%A7%98%E8%A8%A3/
- sadolpedal.hatenadiary.jp. (2024, September 20). ロードバイク通勤は腕が痛くなる?ポジション調整の失敗と対策. Retrieved September 17, 2025, from https://sadolpedal.hatenadiary.jp/entry/2024/09/20/155355
- スポーツナビ. (2019, May 14). ポイントは3つ。ロードバイクの基本フォームのポイントとアイテムチェック. Retrieved September 16, 2025, from
https://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201905140027-spnavido - Y’sRoad. (n.d.). フィッティングについて. Retrieved September 17, 2025, from https://www.ysroad.co.jp/support/bio/fitting.html
- Y’sRoad 川崎. (2024, June 1). 【HOW TO】誰も教えてくれない ロードバイク 肩 腕 手の痛み解消法. Retrieved September 17, 2025, from
https://ysroad.co.jp/kawasaki/2024/06/01/152895
- Y’sRoad 新橋. (2024, October 25). 【からだを学ぶ】フィッティングその3:「ハンドル」の[位置]の. Retrieved September 17, 2025, from
https://ysroad.co.jp/shimbashi-triathlon/2024/10/25/99160