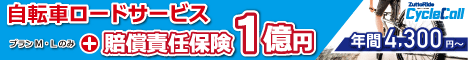- なぜあなたのFTPが「4.0 W/kgの壁」で頭打ちになっているのか、その本当の理由が腑に落ちます。
- 難しい理論はさておき、「エンジンの排気量」という例えでVO2maxの重要性がスッと頭に入ってくるでしょう。
- 明日からZwiftや実走で試せる、具体的で時間効率の高いトレーニングメニューが手に入ります。
- 40代からでも安全かつ効果的にVO2maxを伸ばし、オーバートレーニングを避ける秘訣がわかります。

はじめに
「最近、FTPの通知がまったく更新されない…」
「いつもの峠で、仲間からジリジリと離されてしまうあの感覚…」
そんな焦りや、ふとした瞬間に感じる無力感に、胸がざわついていませんか。 特にロードバイク歴が数年を超え、ただがむしゃらに走るだけでは伸びなくなった40代以上のライダーにとって、これは痛いほど共感できる悩みでしょう。
ペダルがやけに重く感じ、自分の限界が見えてしまったような、そんな寂しさ。でも、安心してください。 そのパフォーマンス停滞、決してあなたの努力不足や年齢のせいではありません。
VO2maxトレーニングという科学的アプローチに光を当てれば、あなたのロードバイク人生は、もう一度、力強く輝き始めるはずです。
【衝撃の事実】なぜ、あなたのFTPは頭打ちになるのか?停滞のメカニズム

FTP(Functional Threshold Power)の成長がピタリと止まるのには、ハッキリとした理由があります。
実のところ、多くのライダーが見過ごしている、パフォーマンスの「天井」にぶつかっているだけなのです。 この章では、その根本原因を一緒に解き明かし、もどかしい停滞期から抜け出すための、確かな一歩を踏み出しましょう。
結論:FTPの”天井”、その高さはVO2maxが決めている
単刀直入に申し上げます。 あなたのFTPがこれ以上伸びるかどうか、その上限、つまりパフォーマンスの”天井”は、VO2max(最大酸素摂取量)という指標によって決まっているのです。
多くの方がFTPの数値を追いかけることに夢中になります。しかし、それはまるで、建物の2階をもっと高くしたいのに、1階の天井の高さを無視しているようなもの。
FTPは、VO2maxという生理学的な上限を、決して超えることはありません。
つまり、いくらFTP向上に特化したトレーニング(SSTなど)を積み重ねても、VO2maxという土台が低いままでは、ある一定のレベルで必ず頭打ちになってしまう。それが現実なのです。
この事実は、あなたのこれまでの常識を少し揺るがすかもしれません。 けれども、このメカニズムを理解することこそが、停滞期から脱出するための、最も重要な鍵となります。
「エンジンの排気量」で腑に落ちるVO2maxとFTPのカンケイ
専門用語が続くと、頭が痛くなりますよね。それではここで一つ、とても分かりやすい例え話をさせてください。
- VO2max = エンジンの排気量
- FTP = そのエンジンで安定して出せる巡航速度
VO2maxとは、あなたの身体が1分間に取り込める酸素の最大量のこと。これが大きいほど、より多くの酸素を筋肉へ送り込み、パワフルなエネルギーを生み出せます。まさに、自動車のエンジンの排気量そのものと言えるでしょう。
かたやFTPは、1時間持続できるパワーのこと。これは、エンジンの性能を活かして安定走行できる「巡航速度」のようなものです。
排気量660ccの軽自動車が、どんなに頑張っても時速200kmで巡航できないのと同じで、VO2maxという排気量が小さいままでは、FTPという巡航速度には自ずと限界が訪れます。
もし今、あなたのFTPが停滞していると感じるなら、それは巡航速度を上げるためのチューニングが限界に達したサイン。
今あなたに必要なのは、エンジンそのものをより大きな排気量のものに載せ替える作業、すなわちVO2maxトレーニングなのです。
40代特有の「伸び悩み」と、その生理学的背景
「若い頃はもっと走れたのになぁ…」
40代に差しかかると、ふと、多くの方がそう感じ始めます。これは気のせいではありません。
加齢とともに、VO2maxは30歳以降、約10%/10年(1%/年)の割合で低下することが複数の研究で確認されています
しかし、ここで希望を失う必要はまったくありません。 適切なVO2maxトレーニングを実践すれば、この生理的な低下に抗い、むしろ20代、30代の頃より高いパフォーマンスを発揮することだって十分に可能なのですから。
40代のトレーニングで何より大切なのは、「がむしゃら」から「科学的」へのシフトチェンジ。若い頃のような無限の回復力は望めません。
だからこそ、一つひとつのトレーニングの「狙い」をはっきりさせ、回復まで含めて計画的に行うことが、停滞期脱出への最短ルートになるでしょう。
ヒルクライムで本当に速くなりたいなら、FTPよりVO2max
特にヒルクライムのような、数分から数十分続く高強度の運動では、VO2maxの高さがパフォーマンスを直接的に左右します。なぜなら、ヒルクライムは、まさにVO2max領域(パワーゾーンでいうL5)での戦いそのものだからです。
FTPが高いことはもちろん重要ですが、それはあくまで「麓から中腹までを楽に走る能力」。勝負どころの激坂区間や、ライバルとのアタック合戦で本当に求められるのは、短時間で爆発的なパワーを生み出し、それを繰り返す能力。
この能力の源こそが、高いVO2maxに他なりません。
「富士ヒルでシルバーリングを獲りたい」「いつもの峠の自己ベストを更新したい」 そう強く願うのであれば、FTPの数値を追いかけるだけでなく、その土台となるVO2maxを引き上げるトレーニングにこそ、今すぐ着手すべきなのです。
【新常識】上位記事が語らない、40代から始めるVO2max向上戦略

VO2maxの重要性は、きっとご理解いただけたことでしょう。 しかし、巷にあふれる情報を鵜呑みにして、ただ闇雲に「全力で追い込む」だけでは、特に私たちのような経験豊富な年代にとっては逆効果になりかねません。
ここでは、他の記事ではあまり語られない、40代からVO2maxトレーニングを成功させるための、4つの新しい常識をお伝えします。
誤解だった「追い込み至上主義」。最強の武器は「計画的な回復」にあり
VO2maxトレーニングは、身体に極めて高い負荷をかけます。若い頃のように、気合と根性だけで乗り切れるものではありません。筋肉や心肺機能が本当に強くなるのは、トレーニングでダメージを受けた後の「回復」の過程でこそ、起こるのです。
kira
私自身、30代の頃にVO2maxトレーニングに夢中になり、「やればやるだけ強くなる」と信じて週に3回も高強度インターバルを繰り返した結果、深刻なオーバートレーニングに陥った苦い経験があります。
パフォーマンスは上がるどころか下がり続け、常に倦怠感が抜けず、レースのスタートラインに立つことすらできませんでした。この失敗から学んだのは、トレーニングの成果は、回復時間中に生まれるという、当たり前で、そして最も重要な事実でした。
高強度トレーニングは槍を研ぐ作業ですが、研ぎすぎれば刃こぼれしてしまいます。 重要なのは、トレーニングと同じくらい「回復」を計画に組み込むこと。
具体的には、高強度のVO2maxトレーニングは週に2回を上限とし、それ以外の日は低強度のライドや完全休養に充てる勇気を持つことです。
時短こそ正義!「ショートインターバル」が多忙なあなたを救う
「VO2maxトレーニングは5分間もがき続けないと意味がない…」 それは、もう古い考え方かもしれません。最新の研究では、もっと短い時間のインターバルでも、同等かそれ以上の効果が得られることがわかってきています。
例えば、「30秒全力+15秒休息」や「40秒全力+20秒休息」を繰り返すショートインターバルです。
この方法の最大のメリットは、短い休息を挟むことで心拍数を高いレベルで維持しやすく、VO2maxが刺激される「質の高い時間」を効率的に稼げる点にあります。
5分間という長い時間、高いモチベーションとパワーを保ち続けるのは精神的にも本当に大変です。
でも、「あと30秒なら頑張れる」という短い目標の連続は、驚くほど継続しやすく、結果として質の高いトレーニングを実現してくれます。
平日の夜、限られた時間で最大の効果を得たいあなたにこそ、試してほしいトレーニング法です。
データに踊らされるな。「GarminのVO2max推定値」との賢い付き合い方
Garminなどのデバイスが示すVO2max推定値。日々の数値に一喜一憂していませんか? 覚えておいてほしいのは、Garminの推定値は長期トレンド観察には有用ですが、個別の数値は±5-10%の誤差があり、特に高強度トレーニング不足や性別による偏りが生じる可能性があります。
では、あの数値は無意味なのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。 賢い付き合い方は、「短期的な数値」ではなく「長期的なトレンド」を見ることです。
- 良い傾向: 3ヶ月、半年というスパンで数値が緩やかに上昇している
- 注意信号: トレーニングしているのに、数週間にわたって数値が停滞・下降している
デバイスが示す数値そのものに振り回されるのではなく、自分のトレーニングが正しい方向に向かっているかを確認するための「コンパス」として活用する。それが、データと上手に付き合う秘訣と言えるでしょう。
【論文より】なぜエリート選手は「二極化トレーニング」を行うのか?
近年のスポーツ科学の世界では、「ポーラライズド(二極化)トレーニング」という考え方が主流になっています。これは、トレーニングの大部分(約80%)を低強度(LSDなど)で行い、残りのごく一部(約20%)を高強度(VO2maxなど)に集中させるというアプローチです。
エリート持久系アスリートの練習内容を分析したある研究では、彼らがFTP付近の中強度(SSTなど)に費やす時間はごくわずかで、練習のほとんどが「すごく楽」か「すごくきつい」の両極端に分かれていたことが示されています(Seiler, 2010)。
これは、中途半端な強度で疲労を溜めるよりも、徹底的に有酸素能力の土台を築き上げ、そして狙いを定めてVO2maxという天井を突き上げる方が、結果的にパフォーマンスを最大化できることを示唆しています。
私たち市民ライダーも、この考え方を取り入れ、トレーニングに「メリハリ」をつけることが重要です。
今日からできる!VO2max向上トレーニングメニュー【Zwift/実走】

理論はもう十分でしょう。ここからは、あなたのトレーニング環境に合わせて、今日からすぐに実践できる具体的なVO2maxトレーニングメニューをご紹介します。
どのメニューを行う前にも、必ず15分以上のウォームアップを忘れずに行ってください。
【室内・Zwift派】王道インターバルと時短インターバルの比較
インドアトレーニングの最大のメリットは、天候に左右されず、集中してパワーターゲットを維持できることです。あなたの目的や使える時間に合わせて、最適なメニューを選んでみましょう。
| メニュー名 | 内容 | パワー目標 (%FTP) | 特徴・こんな人におすすめ |
| 王道:クラシック 5×5 | 5分走+5分回復 × 3〜5セット | 106〜110% | 効果は絶大だが精神的に最も厳しい。VO2maxの基礎を築きたい、自分を追い込みたい日に。 |
| 時短:ショートインターバル 40/20 | (40秒走+20秒回復) × 10回 × 2〜3セット (セット間5分回復) | 115〜120% | 短時間で心拍数を効率的に引き上げられる。平日の夜など、時間がない中で効果を出したいあなたに最適。 |
| 反復能力強化:マイクロインターバル 30/15 | (30秒走+15秒回復) × 13回 × 3セット (セット間3分回復) | 115〜120% | レース中のアタック合戦に強くなる。回復時間が短いため難易度は高いが、反復持久力向上に効果的。 |
Zwift人気ワークアウト「The Gorby」を120%活用する方法
Zwiftの数あるワークアウトの中でも、VO2max向上メニューとして特に有名なのが「The Gorby」。5分間の高強度走を5本繰り返すシンプルな内容ですが、完遂するのは至難の業です。
このワークアウトの効果を最大化し、最後までやり遂げるためのコツを伝授します。
- 序盤の罠にハマるな:
1、2本目はアドレナリンが出てつい頑張りすぎてしまいがち。しかし、ここでパワーを上げすぎると後半に必ず失速します。指定されたパワー範囲の下限(110%)を淡々と維持することに徹しましょう。 - ケイデンスを意識する:
ギアを少し軽くし、ケイデンス(95〜105rpm)を高く保つことで、心肺機能への刺激を最大化し、脚への負担を軽くできます。 - メンタルハック:
「あと5分」と考えると心が折れます。「次の1分を頑張ろう」「あと30秒」と、目標を細かく分割して集中しましょう。
The Gorbyは、あなたのフィジカルだけでなくメンタルも鍛え上げてくれる最高のワークアウトです。
【実走派】パワーメーター不要!近所の坂道を活用した高強度インターバル
パワーメーターがなくても、VO2maxトレーニングは可能です。必要なのは、3〜5分程度で登り切れる、あなたのよく知る「いつもの坂」だけ。
方法:
- その坂を「もうこれ以上は無理だ」と感じる一歩手前の強度で、全力で登ります。
- 下りはゆっくりと、息を整えるための回復時間に使います。
- これを5〜8本繰り返します。
強度の目安:
- 主観的運動強度(RPE): 10段階中「8〜9(かなりきつい〜非常にきつい)」
- 心拍数: 最大心拍数の90%以上
- 会話テスト: 短い単語を発するのがやっとで、会話は全くできないレベル
パワーという絶対的な指標がない分、自分の身体の声と真剣に向き合うことが重要です。風を感じ、景色が変わる屋外でのトレーニングは、インドアとはまた違った充実感を与えてくれるはずです。
失敗しないための「頻度」と「回復」の科学

VO2maxトレーニングは劇薬です。正しく使えば絶大な効果を発揮しますが、使い方を誤れば深刻な副作用(オーバートレーニング)を引き起こします。
この章では、そのリスクを賢く管理し、トレーニング効果を最大化するための「守りの科学」について解説します。
VO2maxトレーニング、最適な頻度は「週2回」が上限のワケ
なぜVO2maxトレーニングは週に2回までが推奨されるのでしょうか? それは、高強度トレーニングが筋肉だけでなく、中枢神経系にも大きな疲労をもたらすからです。
筋肉の回復には48時間もあれば十分かもしれませんが、ホルモンバランスや自律神経といった神経系の回復には、それ以上の時間が必要になることがあります。
週に3回以上も高強度トレーニングを行うと、この神経系の回復が追いつかず、疲労が雪だるま式に蓄積してしまうのです。
各種スポーツ科学研究では、高強度インターバルトレーニングは週に2-3回が効果的と報告されている研究が非常に多く、それ以上の頻度はオーバートレーニングのリスクを増加させます。
焦る気持ちは痛いほどわかりますが、急がば回れ。質の高いトレーニングを続けるためにも、「週2回まで」というルールは必ず守りましょう。
トレーニング効果を最大化する「超回復」の3要素
トレーニングの成果は、トレーニング中ではなく、その後の回復中に生まれます。この「超回復」を促し、効果を最大化するために不可欠な3つの要素をご紹介します。
- 栄養(特にタンパク質と糖質):
トレーニング直後の30分間は、身体が栄養を最も吸収しやすい「ゴールデンタイム」。ここでタンパク質(筋肉の修復材)と糖質(エネルギーの再補充)を速やかに摂ることが、回復を早め、次のトレーニングの質を高めます。プロテインや和菓子などが手軽でおすすめです。 - 睡眠:
睡眠中は、身体の修復と成長を促す「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。最低でも7時間以上の質の高い睡眠を確保することが、どんな高価なサプリメントにも勝る回復薬となります。 - 積極的休養(アクティブリカバリー):
完全な休養も重要ですが、トレーニング翌日に30分程度の軽いライドなどを行うことで、血流が促進され、筋肉中の疲労物質の除去を助ける効果があります。だるい日こそ、軽くペダルを回してみましょう。
これは危険信号!オーバートレーニングの兆候とセルフチェック
自分では気づかないうちに、オーバートレーニングに陥っているケースは少なくありません。身体が発する危険信号を見逃さないように、以下のリストでチェックしてみてください。
一つでも当てはまる状態が数日間続くなら、トレーニングの強度や頻度を見直す必要があります。
| チェック項目 | 詳細 |
| パフォーマンスの低下 | いつもと同じトレーニングなのに、パワーが出ない、タイムが落ちる。 |
| 安静時心拍数の上昇 | 朝、目覚めた直後の心拍数が、通常時より5〜10拍/分以上高い。 |
| 気分の落ち込み・イライラ | 何事にもやる気が起きない、些細なことでイライラする。 |
| 睡眠の質の低下 | 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める。 |
| 食欲不振 | 常に胃がもたれている感じがして、食欲がない。 |
| 風邪をひきやすい | 免疫力が低下し、ちょっとしたことで体調を崩しやすくなる。 |
回復を制する者が、パフォーマンスを制す
結局のところ、本当に強いアスリートとは「強い練習ができる選手」ではありません。 「強い練習から、いかに賢く、そして速く回復できるか」を知っている選手です。
あなたの身体は機械ではありません。日々のコンディションは必ず変動します。計画通りにトレーニングをこなすことだけが正義ではないのです。時には勇気を持って休むこと、計画を変更することが、長期的に見ればあなたをより強くしてくれます。
回復はトレーニングの一部であり、最も重要なスキルの一つ。 このマインドセットを持つことこそが、40代からのロードバイクライフを成功させる最大の秘訣と言えるでしょう。
年間計画にVO2maxトレーニングを組み込む戦略的ピリオダイゼーション

最高のパフォーマンスは、思いつきのトレーニングではなく、年間を通じた論理的な計画、「ピリオダイゼーション(期分け)」によってもたらされます。VO2maxトレーニングという強力な武器を、いつ、どのように使うべきか。その戦略について解説します。
なぜ「基礎期」にVO2maxトレーニングをやってはいけないのか?
ピリオダイゼーションでは、シーズンを大きく「基礎期」「強化期」「ピーク期」などに分けます。多くのライダーが犯しがちな間違いが、オフシーズンである「基礎期」から高強度のVO2maxトレーニングを始めてしまうことです。
基礎期に行うべきは、LSD(Long Slow Distance)のような低強度・長時間のトレーニング。これには、毛細血管網を発達させ、筋肉の酸素利用能力を高めるという、非常に重要な目的があります。 この地道な土台作りを怠り、いきなりVO2maxトレーニングに飛びついても、実は高い効果は望めません。
VO2maxトレーニングは槍の穂先を鋭く研ぐ作業。そして基礎期は、その槍の本体を頑丈に造る作業です。 弱く、粗雑に造られた槍を研ごうとしても、槍はポキリと折れてしまうだけ。
まずはじっくりと有酸素能力の土台を築き上げることが、結果的にあなたのパフォーマンスを、より高いレベルへと導いてくれるのです。
目標レースから逆算!VO2max強化ブロックの最適なタイミング
では、VO2maxトレーニングはいつ行うのが最も効果的なのでしょうか。 答えは、最重要レース(Aレース)の8〜12週間前から始まる「強化期」です。
VO2maxトレーニングによって得られる生理的な適応は、効果が高い反面、その持続期間は比較的短いという特徴があります。シーズン序盤から頑張りすぎても、肝心のレース時には効果が薄れてしまう可能性があるのです。
目標レースから逆算して、
- 基礎期(〜12週前): LSD中心で有酸素基盤をどっしりと構築
- 強化期(12〜4週前): SSTやVO2maxトレーニングを導入し、天井を突き上げる
- ピーク期(4週前〜): 練習量を落とし、レース特異的な強度で最終調整
このように計画的に配置することで、心身ともに最高の状態でスタートラインに立つことが可能になります。
【モデルプラン】富士ヒルクライムでシルバーを獲るための年間計画
具体的なイメージを持っていただくために、「6月の富士ヒルクライムでシルバー(75分切り)達成」を目標とした、年間トレーニングプランのモデルケースをご紹介します。
| 時期 | フェーズ | トレーニングの主な目的 | メニュー例 |
| 12月〜2月 | 基礎期 | 有酸素基盤の構築、ペダリングスキル向上 | ・週末:LSD (3〜4時間) ・平日:SST (20分×2) |
| 3月〜4月 | 強化期① | FTPの底上げ、VO2maxへの準備 | ・週末:LSD+峠走 ・平日:SST (30分×2), VO2max (5分×3) 導入 |
| 5月 | 強化期② | VO2maxの最大化、レースペースへの適応 | ・週末:レースペース走 ・平日:VO2max (5分×5), ショートインターバル |
| 6月前半 | ピーク期 | 疲労抜き(テーパリング)、最終調整 | ・トレーニング量を半分に落とす ・週1回、短いVO2max刺激を入れる |
| 6月下旬 | レース当日 | – | – |
これはあくまで一例です。重要なのは、あなたの目標から逆算して計画を立て、各時期でやるべきことを明確にすることです。
まとめ:停滞の壁を壊し、過去最高の自分へ

この記事では、ロードバイクのパフォーマンス停滞、特に40代で多くの方が直面する「FTPの壁」を打ち破るための鍵として、VO2maxトレーニングの重要性と、その科学的かつ実践的なアプローチについて解説してきました。
本記事の要点チェックリスト
- FTPの伸び悩みは、その上限を決めるVO2maxがボトルネックになっている。
- VO2maxは「エンジンの排気量」。これを大きくしない限り、パフォーマンスに限界が訪れる。
- 40代からは「気合」より「科学」。計画的な回復こそが最強の武器である。
- 多忙な現代人には、時間効率の高い「ショートインターバル」が有効。
- 高強度トレーニングは「週2回」まで。オーバートレーミングの兆候を見逃さない。
- 年間計画を立て、目標レースから逆算してVO2maxトレーニングを戦略的に配置する。
次のステップ:まずは、週に一度の挑戦から
理論を知るだけでは、あなたのパワーメーターの数値は1ワットも上がりません。 大切なのは、今日学んだことを「行動」に移すことです。
完璧な計画を立てる必要はありません。 まずは今週、あなたのトレーニングスケジュールの中に、たった1回だけ。今日ご紹介したVO2maxインターバルメニューを取り入れてみませんか?
それは、Zwiftのショートインターバルかもしれませんし、近所の坂道を全力で駆け上がる一本かもしれません。
たったそれだけの変化が、あなたの身体に新しい刺激を与え、眠っていたポテンシャルを呼び覚ます、大きな、大きな一歩となります。 もう「歳のせいだ」と諦める必要はありません。科学を味方につけ、もどかしい停滞の壁を打ち壊し、来年のレースで、過去最高の自分に出会いましょう。
参考文献・引用元リスト
- Rønnestad, B. R., Hansen, J., & Ellefsen, S. (2015). Short intervals induce superior training adaptations compared with long intervals in cyclists: An effort-matched approach. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 25(2), 143–151.
https://doi.org/10.1111/sms.12165 - Seiler, S. (2010). What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? International Journal of Sports Physiology and Performance, 5(3), 276–291.
https://doi.org/10.1123/ijspp.5.3.276
- Tabata, I., Nishimura, K., Kouzaki, M., Hirai, Y., Ogita, F., Miyachi, M., & Yamamoto, K. (1996). Effects of moderate-intensity endurance and high-intensity intermittent training on anaerobic capacity and VO2max. Medicine & Science in Sports & Exercise, 28(10), 1327–1330.
https://doi.org/10.1097/00005768-199610000-00018